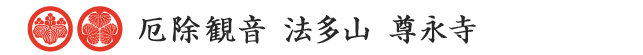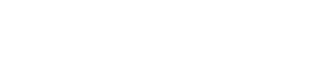星満夜
HOSHIMITSUYO
九月下旬~十月上旬の新月の週末
星と法多山
一つのエピソードと
一つの物語
一つのエピソードと
一つの物語
古来、「星見の僧」と呼ばれる係があったほど、仏教と星は密接な繋がりがあります。法多山では現代においても、星空を眺め、宇宙の広さを感じ、お寺に親しんでもらうため、法多山本堂前で、美しい星を眺めるイベントを年に一度開催しています。天文観測教室をはじめ、飲食の出店、ワークショップなど多くの催しで賑わいます。

年に一度、残暑も少し落ち着きをみせる9月下旬から10月の上旬。
新月の夜の週末に、法多山では、「星満夜(ほしみつよ)」と呼ばれる催しが行われます。
新月とは、この大きな天体の営みの中で、地球から見て、月が見えていない状態のことを指します。地球と太陽の間に月があり、夜空に月がうかばない特別な夜です。
輝く月がうかばぬこの夜は、真の闇に閉ざされるかと思いきや、一転して美しく輝く小さな星を見るのに最適となります。
この「新月の夜」に行われるのが星満夜です。
星満夜という催しが行われるようになった、ちょっとした「エピソード」と、なぜ、高野山真言宗のお寺である法多山が「星」にこだわるのか?という古来から伝わる「物語」をご紹介いたします。
新月の夜の週末に、法多山では、「星満夜(ほしみつよ)」と呼ばれる催しが行われます。
新月とは、この大きな天体の営みの中で、地球から見て、月が見えていない状態のことを指します。地球と太陽の間に月があり、夜空に月がうかばない特別な夜です。
輝く月がうかばぬこの夜は、真の闇に閉ざされるかと思いきや、一転して美しく輝く小さな星を見るのに最適となります。
この「新月の夜」に行われるのが星満夜です。
星満夜という催しが行われるようになった、ちょっとした「エピソード」と、なぜ、高野山真言宗のお寺である法多山が「星」にこだわるのか?という古来から伝わる「物語」をご紹介いたします。

エピソードの始まりは電灯でした。夜に境内を照らす「外灯」です。ある夜、法多山の住職が本堂の外灯を消し、空を見上げた時、頭上に輝く、美しい数千もの星々がありました。その日は、月が隠れる「新月の夜」だったのです。
法多山の本堂は、大きな長い石段を登った山の中にあります。周囲は森に囲まれ、街の灯りが届くことはありません。星の観察には最適な環境であったのです。
天体観測の専門家は、光届かぬ深山の頂き近くで星を観察するといいます。しかし、一般の方がアクセスの悪い観測地に行くことは困難であろう…、整備された法多山の本堂前の広場で、外灯を消せば、こんなにも美しい星が私たちの頭上に輝いている。その姿を多くの方に見てもらいたい。
そして始まったのが「星満夜」という催しです。今では天体観測や様々な体験や飲食の出店など、多くの人で賑わいます。
では、なぜ?お寺である法多山尊永寺がわざわざ「星を見る」ための催しを毎年行っているのか?
法多山はなぜ、星にこだわるのか?
それには、この国の平安時代からの、長い歴史に刻まれた一つの「物語」があります。
法多山の本堂は、大きな長い石段を登った山の中にあります。周囲は森に囲まれ、街の灯りが届くことはありません。星の観察には最適な環境であったのです。
天体観測の専門家は、光届かぬ深山の頂き近くで星を観察するといいます。しかし、一般の方がアクセスの悪い観測地に行くことは困難であろう…、整備された法多山の本堂前の広場で、外灯を消せば、こんなにも美しい星が私たちの頭上に輝いている。その姿を多くの方に見てもらいたい。
そして始まったのが「星満夜」という催しです。今では天体観測や様々な体験や飲食の出店など、多くの人で賑わいます。
では、なぜ?お寺である法多山尊永寺がわざわざ「星を見る」ための催しを毎年行っているのか?
法多山はなぜ、星にこだわるのか?
それには、この国の平安時代からの、長い歴史に刻まれた一つの「物語」があります。

その昔、高野山真言宗の開祖空海は、1200年以上前に、今の中国、唐に渡り、密教をこの国に伝えました。
弘法大師は、仏教の秘伝である密教だけでなく、当時最先端の科学技術もこの国にもたらしました。その一つが、西洋、中東、インド、シルクロードを伝わった占星術、つまり星占いです。
弘法大師によって「東洋占星術」の大著『宿曜経』がもたらされ、その後、彼の弟子たちによって「東洋占星術」の集大成「宿曜道」が完成し「宿曜道」は「宿曜師」と呼ばれる僧侶たちの選任とされ、平安の世の信仰や生活の支えとなりました。
その中には、現在でも多くの人が知る12星座やホロスコープなども含まれています。
昔の日本、とりわけ平安時代には、星の動きを調べるのは、専ら真言宗の僧侶(真言僧)の役目でした。実際には「星を見る」といっても「天体観測」というより「信仰上の星の動き」つまりはその年の星周りや守護星によって、日にちや人々の吉凶を判断する「占星術(星占い)」です。
1200年前、平安の世からこの国に脈々と伝わる使命。この国の星を見護るのは真言宗の僧侶の務めなのです。
真言宗の僧侶がこの国に伝え広めたものは、今も残されています。
弘法大師は、仏教の秘伝である密教だけでなく、当時最先端の科学技術もこの国にもたらしました。その一つが、西洋、中東、インド、シルクロードを伝わった占星術、つまり星占いです。
弘法大師によって「東洋占星術」の大著『宿曜経』がもたらされ、その後、彼の弟子たちによって「東洋占星術」の集大成「宿曜道」が完成し「宿曜道」は「宿曜師」と呼ばれる僧侶たちの選任とされ、平安の世の信仰や生活の支えとなりました。
その中には、現在でも多くの人が知る12星座やホロスコープなども含まれています。
昔の日本、とりわけ平安時代には、星の動きを調べるのは、専ら真言宗の僧侶(真言僧)の役目でした。実際には「星を見る」といっても「天体観測」というより「信仰上の星の動き」つまりはその年の星周りや守護星によって、日にちや人々の吉凶を判断する「占星術(星占い)」です。
1200年前、平安の世からこの国に脈々と伝わる使命。この国の星を見護るのは真言宗の僧侶の務めなのです。
真言宗の僧侶がこの国に伝え広めたものは、今も残されています。

真言密教に伝わり、法多山にも残される「胎蔵曼荼羅」と呼ばれる絵図があります。「金剛界曼荼羅」と一対となり真言密教の真理・大宇宙(森羅万象)を表したものであり、弘法大師が唐から持ち帰ったものです。
この「胎蔵曼荼羅」には大日如来を中心に如来や菩薩など約400体の仏様が描かれていますが、中にはシヴァ神など古代インド神話の神々なども描かれています。
曼荼羅の一番外側「外金剛部」の何箇所かをクローズアップしてみると…、羊宮、牛宮、男女宮、蟹宮、獅子宮、少女宮、秤宮、蝎宮、弓宮、摩竭宮、瓶宮、双魚宮…、西洋占星術の12星座に相当するものが描かれています。
秤宮はてんびん座、蝎宮はさそり座、双魚宮はうお座など、現在に伝わる12星座とほぼ同じものが記されているのが、空海が持ち帰った「曼荼羅」でした。
法多山尊永寺は、空海、弘法大師を祖とする、高野山真言宗の別格本山です。星を見る催し、平安の世から星を見護る僧侶の宗派、真言宗のお寺である法多山尊永寺で「星満夜」が行われる意味と物語はここにあります。
星の光が私たちに見えるまでには、何万光年もかかると言われます。遥か彼方から何万何千年もかけて届く、煌めくような小さな無数の光、歴史の中で埋もれそうな大切なことも同様なのかもしれません。
月という巨大な輝く存在の消えた夜に輝く美しい無数の星。
闇の中、空を見上げたら私たちの頭上には、数え切れないほどの美しい星が輝いている。そんな大切なことを法多山で輝く星を見上げ、今一度思い出してください。
この「胎蔵曼荼羅」には大日如来を中心に如来や菩薩など約400体の仏様が描かれていますが、中にはシヴァ神など古代インド神話の神々なども描かれています。
曼荼羅の一番外側「外金剛部」の何箇所かをクローズアップしてみると…、羊宮、牛宮、男女宮、蟹宮、獅子宮、少女宮、秤宮、蝎宮、弓宮、摩竭宮、瓶宮、双魚宮…、西洋占星術の12星座に相当するものが描かれています。
秤宮はてんびん座、蝎宮はさそり座、双魚宮はうお座など、現在に伝わる12星座とほぼ同じものが記されているのが、空海が持ち帰った「曼荼羅」でした。
法多山尊永寺は、空海、弘法大師を祖とする、高野山真言宗の別格本山です。星を見る催し、平安の世から星を見護る僧侶の宗派、真言宗のお寺である法多山尊永寺で「星満夜」が行われる意味と物語はここにあります。
星の光が私たちに見えるまでには、何万光年もかかると言われます。遥か彼方から何万何千年もかけて届く、煌めくような小さな無数の光、歴史の中で埋もれそうな大切なことも同様なのかもしれません。
月という巨大な輝く存在の消えた夜に輝く美しい無数の星。
闇の中、空を見上げたら私たちの頭上には、数え切れないほどの美しい星が輝いている。そんな大切なことを法多山で輝く星を見上げ、今一度思い出してください。